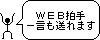ヤンデレからほのぼのまで 現在沈没中
Contents
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
年末年始企画!
ルカ×ミクで切ないけどハッピーエンド なお話
小さなノック音で目が覚めた。
カーテンの隙間から見える空は黒い。
まだ朝も遠くにあるようで、時計も3を過ぎた辺りだ。
こんこん、とさっきよりも控えめなノックに、私はベットから立ち上がる。
ドアを開ければ、そこにいるのは予想通りの子だった。
翡翠の様な綺麗な髪を結んでいないからか、いつもとは違う雰囲気。
いえ、髪だけが原因ではないみたい。
「ルカ姉さん」
暗くて顔はよく見えないものの、聞こえてきたのは予想通りの不安げな声。
どうしたの、なんて尋ねるまでもないほど、繰り返された事だった。
少しでもミクの不安が拭われるように、小さく微笑んで手を引く。
「入って。廊下は寒いでしょう」
部屋の前で長い時間迷っていたのか、ミクの手は冷たかった。
鍵がかかってるわけではないし、冬の夜は廊下とはいえ冷えるのだから、入ってきてしまえばよかったのに。
まだこの子は、私を頼る事に躊躇いを感じるようで、それが少しだけ寂しく感じる。
二人でベットに腰掛けると、ミクがじっと私を見た。
さっきより距離が近くなったからか、ミクの瞳が滲んでいるのがわかる。
それが零れる前に、指で掬った。
そのまま手を伸ばして、ギュッと引き寄せる。
小さな声が私を呼んで、ミクの冷たい手が私の背中に回った。
とくり、と胸に伝わってくるのは、人間の心臓を模しただけの機械の塊が生む、ミクが動いてることの証。私の音も、ミクに伝わっているのだろう。
お互いの胸の音を聞くなんて、そう誰とでもできることじゃない。
けれどミクは、誰とでも交わせる言葉を使って、私に言ってくれはしない。堪えきれない不安から、何度も私の所に来るのに、その不安が何なのか、私は知らない。
そこにいるだけでいいと、そう言って笑うから、なにも聞けなくなる。
このまま溶け合えればいいのに。
触れている場所からどろどろと、一緒になってしまいたい。そうすれば、言葉にしなくてもわかるのに。
温くなったミクの手を背中に感じながら、くだらない事を考える。
ふいに、ミクの腕がぴくりと動いた。
もぞ、と私の腕から逃れるように動くから、思わず強く抱き締めてしまう。
ミクはそれに抗わず、抱き着いた私をそのままにして、代わりに小さな声で囁いた。
「ルカ姉さん、泣いてる?」
「 え? 」
そう言われて、自分の頬が濡れているのに気付く。無意識のそれは不様にも、ミクの肩にも零れたらしい。
なにをしているのだろう。不安がり私の部屋に来たのは、ミクだったのに。私が泣いているんじゃもともこうもない。
慌てて拭おうとすると、その隙にミクが抱き着いていた腕を解いて、さっきよりも少し距離があいた場所で私を見つめた。私は、それを見つめ返すことができなかった。
ミクは、多少なりとも私を頼って、訪ねてくれるのに。涙を流すような弱い私を、ミクは頼ってくれるのだろうか。
どんなミクの瞳がどんな色になっているのか、それが怖くて、顔を上げられない。それに、みっともないことに、その間も涙は止まらないのだ。
「 ごめんなさい 」
それは、どういう意味?
言葉が漏れる前に、細い指が顎に添えられ、ゆるやかに顔を上げさせられる。
視界いっぱいにミクがいて、気が付けば頬を舐められていた。
驚いて、固まっていると、涙も止まったようで。
それに気付くとミクが離れて、恥ずかしそうに顔を赤らめる。
状況が理解できない私は、遅れてきた言葉を呟くしかなかった。
「 なんで、謝ったの?」
「う ん…あのね、ルカ姉さんが泣いてるの見るの、初めてだったから、綺麗だなぁって、思っちゃったの」
「え?」
「ごめんなさい。本当は、ルカ姉さんを慰めなくちゃいけなかったのに。……堪えきれなくて」
さっき舐めた所をちらりと見て、ミクは顔を更に赤くする。
「あと今まで、私ばっかり泣いてたから…ルカ姉さんが泣いてくれて、嬉しかった」
「でも、ミクが泣きそうなのに、私が泣いたら仕方がないじゃない…ミクは、私を頼って来てくれるんじゃないの?」
「うん。でもね、ルカ姉さんに甘えるのと同じくらい、私、ルカ姉さんを甘やかせたいの」
細い腕が私を抱きしめる。力は緩やかなもので、その暖かさに、泣きそうになる。
堪えたと思ったそれは、髪を撫でる優しい手に、いとも簡単に決壊した。
小さな子供のような嗚咽に混じって、ミクの囁きが耳元で聞こえる。
「ルカ姉さん、お話しよう。不安も全部、私にちょうだい」
「今、泣いてるのは、…ほっとしたのかもしれない。多分…嬉しかったから。でも、最初に泣いたのは…」
「私に言いたくない?」
言葉に詰まると、ミクは勘違いをしたようで、声に悲しさを滲ませる。
「そういうのとは違う。わからないの」
「わからなくなっちゃったってこと?」
「そうかもしれないわ」
なぜ泣いたのか、確信を持って言えなかった。
泣いていたのに気づかなかったのだから、当たり前なのかもしれないけれど。
ミクが何を思っているのがわからなかったから、とか、そういう理由とも違う気がして。
ミクは嘘だと思うだろうか。
表情が見えないせいで、沈黙がそのまま不安に繋がってしまう。
それでも、返ってきたものは不信ではなかった。
「そっか。なら、私と同じだったらいいな」
「ミクと?」
「うん。すごく悲しかったりしてもね、ルカ姉さんと一緒にいれば、大丈夫になってなんであんなに悲しかったのかとか、わからなくなるの」
あまりにもミクらしい、暖かさ。
それは、私の中に蟠っていたものを溶かして。
こみあがる愛しさをキスにかえると、ミクが小さく笑う。そのまま二人で、ベッドに倒れ込んだ。
頬を撫でる手にはもうしっかりと、あたたかな温度が移っていた。
PR