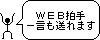ヤンデレからほのぼのまで 現在沈没中
Contents
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
年末年始企画!
おせち作りに奮闘するリンと見守る亜種組 です
ギャグ調で、主にリンとメイト
2009年も残り半日を切り、慌ただしい大掃除も終えて、メイトとカイコは部屋でまったりと過ごしていた。
夕飯の頃になればアカイト達が集まってくるせいで狭苦しくなる部屋も、二人しかいなければ十分な広さだ。
メイトの友人がオススメしたDVDを見ながら適当に喋っていると、てーっててっててーてー、と、気の抜けるメロディが銃声に混じる。
まだそんな時間じゃないはずだとメイトが首を傾げると、カイコが厳ついフォルムの携帯を取り出す。メールの着信音だった。
じっと画面を見つめた後、ことりと首を傾げてメイトを見る。
「アカイトが、もう来ても平気かって言ってるんですけど、大丈夫ですか?」
「あぁ、大丈夫だろ」
「じゃあ、返信しますね」
ぽちぽちとボタンを押しはじめたカイコをちらりと視界に入れつつ、メイトはふと浮かび上がった疑問について考える。
しかし結論が出る前に、些細な事だろう、と思考を放棄して視線を再び画面に戻した。
主人公とライバルが共闘した銃撃戦が終わり、ついに最後の戦いが始まる、といったところでピンポンとインターホンが鳴る。
盛り上がるシーンだから、とメイトはその音を気にかけもせず、映画を見続けていた。苦笑いをしてカイコが立ち上がる。
しかしカイコが迎えに出る前に、ずかずかという足音と共にリビングのドアが勢いよく開かれた。
何事かとメイトが振り返れば、そこにいたのは赤ではなく黄。
ビニール袋を手に鬼のような気迫を出している妹分にメイトはやや驚いたが、またか、と小さく笑う。
先程生まれた小さな疑問も、リンの後ろに続いたアカイトの苦笑いで合点がいく。
台所かりる!とメイトに宣言したリンは、カイコを連れて部屋の奥に行き、やや疲れた様子のアカイトはカイコが座っていた場所に腰を下ろした。
お、これ見てんの、と画面を見て呟くアカイトに応えて、メイトが面白そうに尋ねる。
「で、今日はどうしたんだ?」
「なんかさー、おせち作るから台所貸せって」
「おせち…?いつもカイトが作ってるだろ」
「んー、対抗したいらしい。まぁいつもの気まぐれだろ?」
「へーぇ。実は花嫁修行かなんかだったりな?」
「はなよめ?!」
勢いよくアカイトが立ち上がって台所へ駆け込んだのを見送り、メイトは笑いながら後を追う。
リンとカイコは身仕度をして、今まさに材料を取り出そうとしたところらしかった。
駆け込んできたアカイトをカイコが不思議そうに見つめ、リンは可愛らしい怒りの声を上げる。
「アカにぃー、手伝ってってさっき言ったじゃん!」
「いや、リン、俺はお前におせちは作らせねぇ!まだ、まだ早い!」
「え?何言ってんのアカにぃ」
「うるせー!材料を砕いちまえば作れねぇだろ!農家のみなさんごめんなさい!だが可愛い妹分は誰にもやらん!」
「あっ、アカイト、」
カイコの前にあった袋を奪い取り、手頃な野菜を床にたたき付けようと中身を引っつかむ。
異常なテンションのアカイトだったが、袋から腕を抜いた所で停止する。
自分が今取り出した物を見つめ、先程とは打って変わって、袋のあった場所にソッと置く。
砕けたレンコンだった。
次々とアカイトが出す野菜は、どれも砕けていたり折れていたりと散々な様子だ。
最後に袋の底に入ってたにも関わらず無傷だった卵パックが置かれると、何か言いたげな視線がリンに注がれる。
「だ、だって、卵は大切に扱わないと…」
「いやでもな、なんで卵より硬い野菜が砕けてんのに卵は無事なんだ?」
「…大切に扱ったから?」
「……………やっぱ俺、手伝う」
静かに腕まくりしたアカイトに満足したようで、ニコッとリンが笑顔になる。
とりあえず無事だった材料を使い料理を始め、その間に駄目になってしまったものを買い直しに行く、という流れになった。
買い出し係はメイトがかってでた。普段は料理をしようとしないアカイトだが、カイトがベースなのでなかなか料理の腕は立つ。それはカイコも同じ事だ。
むしろ、ピータンと納豆などを組み合わせた異様な創作料理でそれなりの味の料理にしてしまうのだから、カイト以上と言えるかもしれない。
ともかく、リン以外の三人のうち一番下手だから、と引き止めるカイコをあしらってメイトは部屋を出た。
野菜が入った袋を両手に下げてメイトが歩く。大晦日ということで近所の商店街が閉まっていたため、少し遠くにある大型スーパーに行くはめになり、随分と時間がかかってしまっていた。
遅いよ!とリンがむくれている顔を想像しながら帰宅すると、シロイト達も既に着いていたらしく、玄関にはたくさんの靴が転がっていた。
ただいま、と声をかけるが返事はない。
漏れてくる声や音から騒いでいるようだったが、誰も応えないのは妙だなと訝しみながらリビングのドアを開ける。
「ぁ…メイト!」
「お?」
開けるやいなや、小柄な体躯がメイトにしがみつく。
部屋にいる者は誰もがキッチンに注目しているらしく、二人には気付いていない。
「どうしたニガイト?デカイ声上げて珍しいな」
「うぅ…死ぬかと思った……助けてよ、メイト…」
「おう、助けるけど、どうし」
メイトの声を遮り、鼓膜に直接叩き込んだような破裂音。びくりとニガイトの肩が跳ねる。
顔を真っ青にし、涙で潤んだ瞳がメイトを見上げた。
「リンがおせち作ってて…」
「あぁ。でもカイコ達が手伝ってんだろ?なんであんな音が出るんだ?」
「……僕も途中から手伝ってたんだ…けど、リンが…僕達が手伝うと…練習にならないって言って………味見するだけで、見守っててって…」
「あー、なるほど」
全てを納得しメイトが頷く。ぽんぽんと深緑の髪を叩いてやると、ニガイトはさらにギュッと抱き着いた。
テーブルに目をやれば、完成したと思わしき料理がいくつかならんでいる。
伊達巻きと栗きんとんは、高級料理家に出されても遜色ほどの完成度だ。その隣の昆布巻きも、多少不格好ながらも努力の跡が伺えて微笑ましいかぎりだ。
しかし蛍光紫色をしたアレや、真っ黒焦げのソレはいったい何なのか。恐ろしくてメイトは口を開けない。蛍光紫のあたりからリンが一人で作り出したのは明白だった。
あれ、とニガイトがソファを指差すと、帯人とアカイトがぐったりと倒れていた。味見を実行したのだろう。
若干引き攣った笑いを浮かべて男二人から目を逸らすと、メイトも台所を覗き込んだ。
包丁を握るリンの手はたどたどしく、ごぼうが切れたり切れなかったりしている。包丁を使っているのになぜさっき破裂音がしたのか、その謎をメイトは考えないようにした。
ざっと見たところ、残っている材料はあと一品分程度で、メイト待ちというところなのだろう。
リンは料理に集中しているらしく、カイコやシロイトからのアドバイスに頷いたりしながらも視線はごぼうから動いていない。メイトにはまだ気づいていないようだ。
どうするべきかと悩むメイトにこちらは気づいたらしく、ネルとルコが縋るような視線を送る。
それに加えて、ニガイトがギュッとメイトの服の裾を握る。
リンが振り下ろした包丁は彼女の手から滑り、壁に突き刺さった。シロイトの頬には、うっすらと傷ができた。
既に、犠牲者は二人。
メイトはとりあえず、買ってきた材料を隠すことに決めた。
------------
タイトルの元ネタはことわざの、
『剃刀の刃を渡る』より。
ちなみに意味は、
[失敗したら大怪我をするような、危険な行動をすることの喩え。]
PR