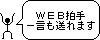[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
リクエストしていただいた、ダブルラリアットをたぬぃ風に。
ルカとカイトのお話。
ラリアット描写はないですがなんか、こう、雰囲気で察していただけると!!
とにかく、誰もいない場所に行きたかった。
ふらふらとまだ慣れない町を歩いて、見つけたのは公園のある一画。一人でいるには少しだけ広いそこは、背の低い木々で死角となっている。
ようやく人のいない場所を見つけた事にほっとして、ルカは芝生に腰を下ろした。
あまり踏まれないせいか、やわらかな芝生は思いの外心地好く、少しだけ迷った後、ぱたんと寝転がる。
明るすぎる夜には星もないのだろうと思っていたのだが、見上げた先にもいくつか輝くものがあった。
それに気分をよくしたルカの口から、小さく星の歌が流れる。
彼女のために作られたそれは、数少ないお気に入りの一つだ。
今まで歌ってきた曲で、ルカがあまり好きではないものはたくさんあった。
どれも良い曲なのは理解できたが、そのほとんどが、自分の好きなものかと問われると、違うと断言するだろう。
それでも、好き嫌い問わずに歌ってきた。
好きではないと口にだしてはいないからか、仕事には支障はないのだが。
時折、ぐらりと視界が傾くようなことがあった。気のせいだろうと放っておいた、その結果がこれだ。
夜中に家を飛び出すなんて、初めての経験だった。
言い争ったわけではなく、それぞれが部屋に戻った後にこっそりと出てきただけなのだが、その理由が、一人になりたい、というものだからか、罪悪感のようなものがルカの中に浮かぶ。
「……はぁ」
酷い不安と焦燥に駆られたのだ。
どの曲も楽しそうに歌う彼や彼女。それに対し、自分は曲を勝手に判断して歌っている。歌うための存在ならば、どちらが失敗なのかは一目瞭然。
家族のように接してくる彼らの輪にうまく馴染みにくいのも、ここからくるのだろうとルカは考えていた。
そして考えれば考えるほど、なにをしようにも身動きがとれないような、なにもできずに処分されるのを待つような不安が襲い掛かってくる。
一人になっても結局は変わらないのなら、罪悪感が大きくなりすぎないうちに帰ろうか。
そう考えてルカがのろのろと上半身を起こしたところで、がさり、音がした。
いくら人の気配がないとはいえ、それなりに遅い時間だ。不審者にでも絡まれたら面倒なことになる、とルカは身構える。
「……あれ?」
葉を掻き分けて現れたのは、カイトだった。
会いたくなくてこうして見つからなさそうな場所に来たというのに、なぜ、とルカの心に八つ当たりに似た苛立ちが生まれる。
それを知らずにカイトは、びっくりしたよ、などと言いながら頭に付いた葉を払った。
「隣いいかな?」
「…どうぞ」
「ありがとう」
ルカが少し移動してスペースを作ると、そこにカイトが座る。
なぜここにいるのかとも聞いてくる事無く、にこにこと楽しそうな顔の彼に、ルカの苛立ちは増していく。
罪悪感があったのも加えて、沈黙に耐え切れなくなったルカが口を開いた。
「ねぇ。あなた、なんでここにいるの?」
「ん?あぁ、たまに来るんだ。今夜は……まぁ、なんとなくかな。ルカは?」
「私は………、私も、なんとなくよ」
「そっか。じゃあ気が合ったのかな」
さすがに、一人になりたかったと言うわけにはいかなかった。ここで言うそれは帰れと同義だ。
ぱたん、と先程のルカと同じようにカイトが芝生に寝転ぶと、楽しそうな顔がよく見えた。
カイトはルカの視線で自分が笑っている事に気付いたようで、あぁ、と苦笑した。
「いや、ここってボーカロイドを集める装置でも埋まってるのかなって思って」
「………なにを言いたいのかわからないわ」
「あー…、ルカってこの場所、誰かに聞いたから来た?」
「いいえ。自分で見つけたけれど」
「なら、やっぱりそうだ」
うんうん、と一人で頷き、カイトが笑う。
「俺もだけどさ、ミクもメイコも、みんなそうなんだよ。なんとなくここを見つけて、たまにここでこうやってると、今みたいに誰かに会うんだ」
「意外ね。あなた達なら、こういう場所を見つけたらすぐお互いに報告しあいそうなものだけど」
「そんなことないよ。ここはなんか…そうだな、秘密基地みたいなものだから。まぁ、結局みんな知ってるけど。でも、居心地いいよね」
声にはださなかったが、それにはルカも同意した。
一人になりたいという理由で探していた場所だが、必ずしも一人になれるわけではないと知った今でも、ここにもうこないという選択肢は彼女の中に生まれてこなかった。
それを不思議に思っていると、今度はカイトの視線がルカに向けられていた。
見返せば、ぎこちなく視線がさ迷い、それと同じようにカイトが口を動かす。
「あの…さ、たまにここ来ると、ミクとか、 泣いてるときがあるんだ。それにまぁ、俺も落ち込んでる時にここ来ることもあるし…」
つまり、なにかあったのかと。
必死に言葉を選びながらそう伝えるカイトに、思わずルカの苛立ちもほぐれる。
小さく笑うと、え、とカイトがぽかんとした目をした。
ルカはまた寝転がり、先程よりも心が軽くなったような気分で言う。
「別に、大丈夫よ。泣きそうになんかなってないわ」
「…そう?」
「えぇ。少なくともカイトに泣いてるのを慰めてほしいと思わないもの」
え、と想像通りのショックを受けた声がする。
お互い仰向けになっているのであまり表情は見えないが、それこそカイトは今にも泣きそうな顔をしているのかもしれない、とルカはまた笑ってしまう。
カイトが口をつぐんでしまったので、どうにかしてそれを堪える。ふぅ、と一つ息をはいた。
「けれど、落ち込むというか、まいってたのは確か。でもそれは、だれかに言う程の事じゃないの」
だから、とルカが続けた。
「そのうち言いたくなったら、傍にいて。それでいいわ」
言い終えて、少し恥ずかしくなったのかルカがカイトに背を向けるように横を向く。
さらりと流れた桃色の髪を見て、カイトは柔らかく笑って、頷いた。
.