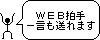ヤンデレからほのぼのまで 現在沈没中
Contents
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
月がきれいだったからうっかり吸血鬼話。
水底ryの随分後ぐらいなのではなかろうか。まぁでもそんな繋がってません
メイトとカイト
血を舐めたりしてます
苦手な方はご注意
薬指を口元に持っていくと、躊躇いがちに白い牙が皮膚に突き立った。
自分の肉に異物が入り込む感覚は、何度経験しても痛みしかもたらさない。
元から自分が無理矢理やらせているのだからと、痛みは表には出していないつもりだったが、慌てたように牙が引き抜かれる。
生まれた二つの傷から溢れる血液にびくりと反応するも、不安げな青い瞳がこちらを見つめていた。
「いいから、さっさと飲め。もったいないだろ?」
「あ、ごめ」
床に斑点を作りはじめた血を、カイトがあわてて舐めとる。
二、三度行えば、指に広がっていた赤色もすぐに無くなり、赤黒い二つの穴からじわじわと血が出てくるだけだった。
こんな量では当然、カイトには足りないわけで。
指をカイトの口から引き抜くと、すっかり吸血鬼のそれになった瞳が追いかけてきた。
「メイト…?」
さっきの躊躇いも血の味に吹き飛んだのか、食料を奪われた、やや不満げな声だった。
「わかってる。口開けとけ」
「…うん」
首やら腕に噛み付かせるのは、俺もカイトも視覚的に勘弁だった。
だから足りない出血量を補うには、こういう二度手間をしなければならない。こいつが美人な女性なら問題なかったのに。
生憎刃物は持ってないから、カイトの鋭い牙を利用して、穴と穴を繋ぐような薄めの傷をつける。
それから薬指をぎゅっと掴めば、さっきよりはましな量がぼたぼたと溢れ出した。
開いたままのカイトの口の上にもっていけば、ごくん、ごくんと指を垂れていく血を嚥下していく。
けれどその勢いも止まりかけてきたので、もう一度血を絞ろうとしたら、カイトが手を掴んだ。
「メイト、もう大丈夫」
「遠慮してんのか?お前の欲しがる血なんざ、俺にはたいした量じゃないから気にすんなよ」
「うーん、そういうことじゃなくて」
カイトは傷に舌を這わせ、血を舐めとり指を清める。
「メイトの血っておいしいから、これで充分なんだ」
蕩けるような笑顔で言われ、そりゃ光栄だ、とメイトは軽口を叩いた。
PR