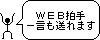ヤンデレからほのぼのまで 現在沈没中
Contents
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
リクエストしていただいた、記憶喪失ネタでございます。
カイトとメイコとアカイトと、ちらっとルカとレン
雨の後の曇り空の下、湿ってしまった落ち葉が敷き詰められた道を一人の青年が歩く。
買い物帰りのようで、両手に食材が詰まった袋を持っており、小さく歌を口ずさんでいた。
空気が湿り、道の隅の水溜まりを跳ねさせて歌うのは、もちろん雨上がりの歌だ。いつもより重い袋を持ち直して、歩道橋の階段を上がり始める。
そんな彼の後ろから、快活な声が彼を呼んだ。
「カイト!」
「ん?」
歩道橋の階段の半ば辺りで振り返れば、カイトと呼ばれた彼の姉、メイコが小さく駆けてきている。
仕事帰りらしく薄化粧した姿を見て、カイトは足を止めた。
同じ段まで上がってきたメイコにおつかれ、と声をかけて、カイトはほほえむ。
「今日は早いね。新しいプロデューサーさんだったんでしょ?どうだった?」
「どうしたもこうしたも…」
元から強い光を湛えている瞳に怒りの色が生まれる。
どうやら仕事中に彼女のお怒りに触れるようなことがあったらしく、カイトはやや身構える。
「あいつ、最悪だったわ!私がスタジオに行ったら、人間みたいだとかいいながら胸やら腰やら触ろうとしてきて…ほんっと腹立つ!私の歌を聴きすらしないのよ!!」
「え………触られたの?」
「んなことさせるわけないでしょう!!マイクスタンドで鳩尾突いてさっさと帰ってきたの!」
怒りを燃え上がらせるメイコの隣で、それならまだよかった、と呟いたカイトをメイコが小突く。
まだもなにも全部だめよ、とメイコがぼやき、一つ息を吐いた。
今の溜息で無理矢理怒りを吐き出したのか、先程よりは落ち着いた様子で、気持ちを切り替えるように階段を一つ上る。
僅かにカイトを見下ろして、そこで彼が持つ袋に気付いたようだった。
「カイト、袋一つもつわ」
「え?どうしたの急に」
「みっともない事知られちゃったから、口封じってとこよ」
「あー…、でもこれ結構重いから、やめておいたほうがいいよ。さっきのこともミク達に言ったりしないし」
「はいはい、人の善意をないがしろにしない」
そう言ってメイコは袋を奪いとったのだが、その重さは彼女の予想を超えており、細い体がぐらりと揺れた。
「 ! 」
「ぁ、 ぶなっ ぁああぁああああっ!」
地面に向かって浮きかけたメイコの体をカイトがすんでのところで抱き留めるが、如何せん、日が悪かった。
雨に濡れた階段はカイトの足をとり、踏ん張りが効かず背中から階段を滑り落ちてしまったのだ。
唐突な事にメイコは声を上げる事もできず、ガツゴツと嫌な音をたてて二人は階段を落ちる。
落ちた、といっても歩道橋の、しかも半ばほどの階段からだ。実際はそう長い間落ちたわけではないのだが、突然の浮遊感に動転した頭では随分長く感じられた。
ようやく止まったらしい、とメイコはいつの間にか閉じてしまっていた瞳をおそるおそる開く。
まっさきに視界に入ったのは青で、いったい何がおきたのかと再び動揺しかけたのだが、それがカイトのマフラーだと気付く。
確認してみれば、カイトに抱き留められたまま落ちたからか、メイコには打ち身の一つもないようだ。
「 あ 、ありがとう」
やや上擦った声で一先ずカイトにそう言ってから、彼の腕をのけてメイコが立ち上がった。
しかしカイトは目を回しているのか、水溜まりに後頭部を突っ込んで倒れたままだ。ちなみに二つあった袋のうちの一つはカイトの腕にひっかかったままで、もう片方は階段で中身をまいて転がっている。
先に袋を回収するべきかと考えていたメイコだったが、起きる気配のないカイトの姿に嫌な予感がよぎる。
「カイト……、ねぇカイト、大丈夫?」
そういえば、カイトの叫び声が途切れたのは階段を落ちきる前だったような、と嫌な予感は増していく。
肩を軽く揺する手に、嫌でも力が入った。
「ねぇ、カイト!大丈夫?!起きて!」
揺すられる度にぱしゃぱしゃと青い髪が水に濡れていき、メイコに焦燥感がつもる。
どうすればいい、どうすれば、という言葉は頭に浮かぶものの、実際にどうすればいいのかまで考える事ができない。思考は空回りをするばかりだ。
ただ肩を揺すって名前を呼び続けていると、ようやくカイトの瞼がぴくりと動いた。
「カイト!」
うぅ、と小さなうめき声と共に瞼が開かれ、のぞいた青色にメイコは安堵する。
ともすれば涙も出そうになりながら、よかった、とメイコが呟く。
「大丈夫?目を覚まさないから、すごく心配したのよ」
「あ、 はい」
とりあえず二人は立ち上がり、メイコは濡れてしまったカイトの髪を拭くものがないかと鞄を探した。
なにか違和感を覚えつつも、メイコは鞄からハンカチを取り出す。
「はい。これ、使って」
「ありがとうございます」
カイトの言葉に、メイコは決定的な違和感がした。そろり、と一度は消えた嫌な予感が戻ってくる。
それがなんなのか頭を捻っていると、あらかたの水気をとりおえたらしいカイトが、ハンカチを畳んでメイコに手渡した。
それを受け取るついでに、本当に大丈夫なのかと再び問い掛けようとしたメイコは、しかしカイトの言葉によって凍りついた。
「本当にありがとうございました。見ず知らずの僕にハンカチを貸してくださるなんて」
「は?」
メイコは違和感の正体に気付いた。カイトが敬語を使い、しかも一人称が 僕 になるのはマスターと、他には初対面の人などあまり交流のない人間に対してのみなのだ。
しかしいつもと違う彼の言葉遣いに以上に、後半の言葉がメイコに強い衝撃を与えた。
「見ず知らず?」
思わず反復してしまった言葉に、カイトは申し訳なさそうな顔をして言った。
「あ……、お会いしたことがありましたか。すみません。
お名前を教えてもらってもいいですか?」
*
「――って事だってさ」
レンがそう長くもない説明を終えて、アカイトを見た。
気にしていないように装っているが、レンもやはり戸惑っているようだ。
「それで、カイトの記憶がトんじゃってる、と」
「そう。人間だとすると、記憶喪失というとこね」
アカイトの言葉に、ルカがそう付け加える。
なにやってんだよ、とアカイトがぼやき、七味煎餅をバキリとかみ砕いた。
記憶が完全に初期化されてしまったのかはわからないが、いわゆる記憶喪失になったカイトはリビングのソファーに座り、所在なさ気に視線をさ迷わせているようだ。
それを見ながら、他の二人と共にテーブルについているアカイトは溜息をついた。
ちなみにメイコは、忘れられた事にあまりにもショックを受けてしまい、部屋に引きこもってしまっている。
「リンとミクはいつ帰ってくんだ?」
「晩御飯前には。今日は全員でご飯を食べるのにあなたまで来るというから、カイトは大量の買物をしなければならなかったのよ」
「なんで俺のせいみたいに言うんだよ、ルカ…」
机に突っ伏したアカイトを気にもせず、ルカは小さな乾燥マグロのキューブを一つ口に放り込む。
食べているのは酒のつまみになるようなものなのに、なんでそんなに優雅に見えるのかなどと、ネルがよくわからない理由で怒っていた事を思い出しつつ、レンは視線で、どうにかしてくれとアカイトに訴える。
仕方ない、とアカイトは煎餅を全部食べ終わると、テーブルをたちカイトの元へと向かう。
青い瞳は特にぼんやりするでもなく、しっかりとアカイトを捉えた。記憶に関して以外は正常に動いているようだ。
「なぁ、本当になんも覚えてねぇの?」
「はい」
「そこの二人も?」
「はい……あの、あなたも、あの二人も、僕と面識があったんですか?」
「面識もなにも、まあ、家族みたいなもん。ちなみにここお前の家なんだけど、見覚えは?」
「いえ。ありません」
そう言ってカイトは悲しげに目を伏せた。
いつもとは全く違う対応に戸惑いながらもカイトに質問していたアカイトは、ちらりとレン達に目をやる。
「なあお前ら、どこまでこいつに話してんだ?」
「ほとんど話してない」
「どう扱えばいいのかわからなかったの。しかたがないでしょう」
「マジか…一から説明しなきゃなんねぇのか」
そもそもどこからどう語ればいいのか、とアカイトが頭を掻きむしる。
落ち着かないカイトをそのままにアカイトがしばらく唸っていると、リビングのドアが開かれた。
誰かこの状況をどうにかしてくれる人であれ、とアカイトが期待に満ちた目で音の方へと振り返るが、慌てて顔を戻す。
何事かと他の二人も目を向ければ、そこには幽鬼のような雰囲気を身に纏ったメイコが佇んでいた。あまりの恐ろしさにレンはおろか、ルカまでもがヒィっと息をのむ。
掠れてはいるものの、地を這い削り取るような圧迫感を伴った声が問いかけた。
「…………カイトは?」
「あ、あ ぁ…まだ、だめ 、みたい」
「………………………」
勇気を振り絞り、いや、拒む事ができなかったのか、そのどちらか定かではないが、レンがどうにかして答えた言葉に対し、メイコは沈黙を返す。
誰ひとりとして動けないプレッシャー。彼女がこの後怒り狂うのか、泣き叫ぶのか、全く予想できないが、どちらにしてもこの3人にとっては対処しきれない事には変わらない。
「……………………………そう」
メイコは近くの椅子に座り、がっくりとうなだれた。
ようやくプレッシャーから解放されたアカイト達は、嫌な汗が伝うのを感じながら、視線で意志を交わす。早くどうにかしないと、こっちがやばい。
うだうだと悩む余裕すら無くなったアカイトが口を開いた。
PR