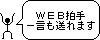[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
元拍手
出演は、
兄さん(死亡)
兄さん(偽物)
レン(壊れかけ)
ミク(病んでる)
というような感じです。
はごろもPさんの、ゆりかごから墓場まで、に多大なる影響を受けております。
ですが、はごろもPさん及び曲とは全く関係のない、たぬぃの妄想ですのでご注意ください。
「 レ、 ン 」
ズルリ、と突き刺していた包丁を引き抜く。
支えを失った体は膝から静かに折れて、トサリと思いの外軽い音をたてた。
服が吸い切れなかった水が床に広がって靴を汚していくのを気にもせず、
名前を呼ばれた少年は、たった今自分が手に掛けた青年に手を伸ばす。
もう二度と力の入ることのない体を抱きしめた少年の胸の内は、歓喜に満ち溢れていた。
歌うために生まれた彼の声帯が最後に唄ったのは、自分の名前。
これはどれほど価値のある事だろうか。
「あは、ははは」
僅かな風にさえ掻き消されそうな、最期の音。その音が自分の名を紡ぐ。
その喜びに、少年は箍が外れたように笑う。
「ははははははははは、はは、ははははははははははは!」
嬉しかった。最後の最期に彼を独り占めできたような気がした。その喜びは本物だった。
それなのに、目から水が流れてくるのが、少年は不思議でたまらない。
「っえ、なに、これ、、な、んで?なんで、おれは、」
一粒の感覚が波紋を呼び、隠れていた理性を引きずり出す。
「なんで俺は、あの人を殺しちゃったんだ?」
歪んだ喜びから放たれ、徐々に少年に犯した罪の重さがのしかかり始めた。
血のぬめりに怯え、にぎりしめていた包丁から手を放す。
まるで包丁によって抑えられていたかのように、左手から全身へと、ガタガタと震えが伝わっていった。
あの人が楽しそうに、他の誰かと話すのを見るのが苦しかった。
誰かの事をうれしそうに語る姿が嫌だった。
なぜ自分にだけ笑ってくれないのか、考えるだけで苦しかった。
それに比べて、あの最期の言葉はあまりにも甘美だった。
甘く、あまぁく、システムの奥深くまで熔かすような熱い響き。
たとえどれだけ熟した果実でも叶わないだろう、思い出すだけでまた体の芯が痺れる甘さ。
それでも、
あの人が気まぐれに繋いでくる手の方が、
優しいその笑顔の方が、
色々な言葉を紡ぐ声の方が、少年の心をより満たしていたことに、ようやく気付く。
「俺は、 おれ は 」
震えが止まらない少年の体とは対照的に、ピクリとも動かない体。
服を通して染み込んでくる血の冷たさに少年は耐え切れなかった。
「うわあああああああ」
抱きしめていた体を乱暴に突き飛ばし、暗い倉庫から逃げ出そうとドアを開ける。
廊下の明るさに備え、目を細めていたが光はさしてこない。
何故だろうと、冷静さを取り戻し始めた少年は恐る恐る顔を上げる。
ドアの前に立ち、蛍光灯の明かりを遮っていたのは、青い髪に黒いコートを着込んだ若い男だった。
少年は慌てて後ろの彼の存在を確認し、また黒いコートの男を見る。
その男は、あまりにも彼に似ていた。
もしやこれは何か悪い夢だったのではないか。
そう、都合のいい願いを込めて、少年は言う。
「カイ 」
だがその名前は男の指によって制され、代わりに男が口を開いた。
「俺は、これからレンを見守る人です。ただそれだけで、他の誰でもない。」
へにゃりと座り込んだ少年と目を合わせるために男もしゃがみこむ。
「ただ、これからどれくらいかはわかりませんが、死の時までレンについていくことになりました。これからよろしくお願いします。」
ふわりと笑うその顔はあの人そのままで、少年の目にまた、涙が滲んだ。
----------
最近、なにかと力が入らない。
ゴロリとベットに転がり見上げる天井も、電気が付いているのにも関わらず前よりも暗く見える。
ついさっきまでの歌の練習も歌詞や音程を間違えてばかりで、マスターも早めに練習を打ち切ってしまった。
この感覚が何かはわからないが、元となった理由に心当たりはいくつかある。
ただそれが、あの人のことかあの男のことか、どちらが本当なのかはわからないけど。
視界を僅かに動かせば、椅子に座ってるあいつが目に入る。
なにも考えていないかのような顔をして、なにをするわけでもなくただ座っている。
あいつが俺の前に出てきてからようやく4日がたった。
その間、あいつは今みたいに電源を切ったかのように動かなかったり、最初のように親しげに話しかけたりしてきた。
そして宣言通り、常に俺の後をついてまわる。
あいつの姿は俺以外には見えないらしく、メイコねぇ達に不審がられることはなかった。
だけどやはり居心地が悪い。
それと、あの人は…、いつの間にかいなくなったってことになっている。
これは俺が隠したわけでなく、本当に 消えていた。
あの後俺はどうにか部屋に逃げ帰って、それからしばらくしてやっと、あの人の体のことを思い出したんだ。
走ってあの部屋に戻ったけど、そこにはあの人の影も形も、血の一滴も残っていなかった。
これだけなら、俺の質の悪い夢だったのかと思えたけど、生憎錆び付いたような血の匂いは部屋に篭ったままで。
そう簡単に逃げれるものではなかった。
なのに、罪は確かに存在するのに、詰られも裁かれもしない違和感。
それは確実に俺の足に絡み付いていて、どこへ行こうにも許してくれない。
この足を掴むものを振りほどく方法、それはきっと。
チラリ、とまたあの男へと視線を移す。
あいつは今度は俺の方に目をやり、にこりと微笑んで何も言わずにドアを指差す。
コンコン
その動作と誰かが部屋にやって来たのは同時だった。
「レン…、入ってもいい?」
その誰か、はミクねぇだった。
いったいなんの用だろう。さっきの歌の練習のことで何か気になる事でもあったのか。
とりあえずドア越しに返事をする。
「あー、うん、入っ「レン」
唐突に言葉を遮ったのはあいつだった。
「レン、最初で最後の忠告をしてあげましょう。」
「は…?何言って……?」
「『隣りに気をつけて』。ただそれだけの事です。」
「……なんだよ、それ」
「いえ、ただの傍観者の戯言です。お気になさらず。」
「なら、いいけど」
「………レン?」
返事がないことを不安に思ったのか、また控え目にミクねぇがドアをノックした。
「ミクねぇ、入っていいよ。鍵かかってないから」
「うん、それじゃあ、」
おじゃまします、とドアが開き、ミクねぇが顔を覗かせた。
-------------
「ミクねぇ、どしたの?」
部屋に入ってもうつむいたままのミクねぇに声をかける。
なんだか元気がないようで、朝からこんな調子だったかなと思い巡らせたら今日はまだミクねぇと会っていなかった。
むしろここ数日、俺があまり部屋から出なかった事も相俟って全然顔を合わせていなかったことに気がつく。
「あのね、レン。聞きたいことがあるの」
急にミクねぇが顔を上げ、俺に詰め寄ってきた。
その怯えたような、切羽詰まった姿に俺はあることに思い当たった。
ミクねぇは、俺があの人を殺した事を知っている?
途端にドクリと心臓が動き始める。
掌に浮かんだ汗が、あの人の血の様に纏わり付いている気がして慌てて気付かれないようにシーツで手を拭った。
今にもガタガタ震え出しそうなミクねぇは、ベットの端まで来て言葉を続ける。
「お兄ちゃんの、事なんだけど、」
その言葉に、思わず肩が跳ねた。いくら平静を装っても今ので何かあるとばれただろう。
ミクねぇはきっと俺があの人を殺してしまったことを知っている。
そして多分俺を責めにきたんだろう。
いや、俺をアンインストールしにきたのかもしれない。
影も形も血の一滴から匂い気配存在、全てをなかったことにする行為。それは俺達にとって最も恐ろしい仕打ち。
だからこそ最悪の事をした俺に相応しい罰だ。だけど、
指先から消失していく感覚、そしてそのあと別の俺が何食わぬ顔でここにいる風景を想像する。
それはあまりにも恐ろしい。怖くて恐くてたまらない。
指先の感覚を確かめるようにシーツを握る。
いやだ、俺は消えたくない。あの人を壊した俺がこんなこと言えるはずないってわかってる。でも俺は消えたくない。消えたくないんだ!
ミクねぇの不安げな顔が目に入る。でも本当は俺をアンインストールしようと企んでるのかも知れない。メイコねぇ達の前に突き出して俺を責めようとしてるのかもしれない。リンの絶望した顔が、メイコねぇの嫌悪に満ちた顔が頭に浮かぶ。いやだ、いやだいやだいやだいやだ!
俺は、まだ消えたくない。みんなと一緒にいたい。だからそのためには、気付いたミクねぇをどっかにやらなくちゃ。殺さなくちゃ、コロサナクチャ、ころさなくちゃ、ころさなくちゃ。
机の引き出しの中にカッターがあったからそれを使おう。そうだ、そうすればいい。机まで走って、振り向いて、突き刺そう。
ミクねぇの口が開く。
「さいごに、なんて言ってたのかな?」
思考が途切れる。
なんだ?
「お兄ちゃん、壊れる前になんていったの?もしかして、やっぱりレンの名前?」
ミクねぇはなにを?
これじゃあまるで
「ああ、やっぱそうなんだね。残念だなあ。最期には私の名前、呼んでほしかったのに。」
俺が殺したのにはとっくに気付いてるのか?
なのに、殺してしまった事は何も責めない。
ミクねぇはどうしちゃったんだ?
一気に頭が冷えていく。
「残念だなあ。悔しいなあ。でもさ、だから別にいいよね?レンは最期のをもらえたんだし、私が、」
あの光景を、急に思い出した。
ただの物置。
だけどいつも通りな事が異常だったあの部屋。
いつの間にか消えていた、あの人の
「私が、お兄ちゃんを持ってってもよかったよね?問題ないよね?大変だったんだよ?お兄ちゃんを崩さないように部屋に持って行って、拡がった血はちゃんと綺麗な布で拭き取って、あれ以上崩壊が進まないように処置して。でも、お兄ちゃんのためだから頑張れたけどね!」
さっきまでの不安そうな姿はなんだったんだ?今にも震えそうだったのは?
嫉妬だったのか?あの人が最期に呼んだだろう俺に嫉妬していた?
俺の事など気にもかけず、ミクねぇはブツブツと言葉を吐き出す。
「でもやっぱりずるいよね。レンだけ最期に名前呼ばれたなんてずるいよ。レンはずるい!私だって呼ばれたかったのに!あ、でも、最期に呼ばれたレンがいなくなっちゃえば、お兄ちゃんが呼んだ最期の人は私になるのかな?」
嫌な、予感がする。
さっきまでの自分を見ているような。
「なるよね、なるよ!きっとなる!だからレン、あのね、死んで!」
ずっと後ろにまわしていたミクねぇが手を振りかぶる。
それは、俺があの人に突き刺したものと同じで。
鈍い刀身は、あの人が、いや、あいつの姿を反射していて。
俺はどうしても、よけることができなかった。
--------------
ざくり、ざくりと二回、俺を突き刺していったミクねぇは、俺があの人を殺した時みたいに取り乱すことすらしないで、上機嫌で部屋から出ていった。
だらだらとちからが抜けていく。
痛みは、痛覚を遮断したからないけれど、き持ちの悪い感覚だけは消えない。
結きょく俺は、アンインストールされはしなかったけど壊れてしまった。
霞みもしない、いつもと同じクリアな視かいには、あいつが微笑みを浮かべてこっちを見ている姿がうつった。ほん当にさいごまで、なにもしてこない。
ああ、どうせなら、死んでしまうのなら、あいつに、あの人に、
かいとにぃにころしてほしかった。
それがむりなことだとは、じゅうぶんしっているけども