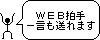ヤンデレからほのぼのまで 現在沈没中
Contents
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
5000回転記念で吸血鬼なお話
カイトとメイトで若干暗い
錆び付いたドアを開けると、真昼間だというのに薄暗い廊下が伸びている。
いつも通りのその様子に少しだけ安心する。この部屋の主は時々へまをして、カーテンを閉め忘れるからだ。
陽光に触れていないせいで冷え切った廊下を進んでリビングに入る。
分厚い遮光カーテンのせいで一つの明かりもない部屋も、メイトは問題なく歩く。とうに馴れた部屋は、見えなかろうが彼には関係ない。
リビングから繋がっているキッチンに持っていたビニール袋を置いて、再び戻るとソファに転がったままのものを蹴り飛ばした。
「おいカイト、起きろー。食い物持ってきてやったから」
「……ん………、…」
蹴り飛ばされた腹を抱えてソファの背を向き丸くなり、起きる気が皆無のカイトにメイトは苦笑する。
そう大きくないソファだというのにそんな姿勢でよく落ちないなと感心しつつ、メイトはその肩に足を引っ掛けてカイトを転がり落とす。
ゴン
鈍い音がしてそれに見合った衝撃がカイトに訪れたのか、床に転がって数秒後、打ち付けた後頭部を押さえながらカイトはゆるゆると瞼を開いた。
彼にしては珍しい不機嫌そうな顔で、ぼんやりと天井あたりをふらふら揺れていた視線がメイトを捕らえる。
「…メイ ト?なに?」
「食い物持ってきてやったから、起きろ」
「いぃ…おれ、のまない……ねむ…し……」
「だから食い物だって。とりあえず作るから、できたら食えよ?」
むにゃむにゃとカイトがまだ何か言っているのを放っておいて、メイトはキッチンに戻ってヤカンに水を入れ火にかける。
作る、といってもメイトにきちんとした料理を作るつもりはなく、ビニール袋の中に入っているのもただのカップラーメンだ。
湯が沸くまでの時間を火薬を入れたりして潰し、ぴぃいと耳障りな甲高い声を上げるヤカンからカップラーメンの中に湯を注ぐ。
タイマーなんてものはなく、ちらりと視線をうつして時計を見る。13時15分。
忘れないように頭の中で反復しつつ、カップをリビングのテーブルに持っていく。
まだ床に転がったままのカイトをまた蹴り飛ばすと、今度はふらふらと立ち上がってテーブルについた。
「あと2分だからちゃんと待ってな」
「……うん、ありがと…」
まだまだ眠そうな彼も思ってみれば当然といえる。午後1時の太陽が元気なこの時間帯は、吸血鬼である彼の活動時間からは程遠いだろう。
やがて時計が18分を指し、カイトがいただきます、と手を合わせてラーメンを食べ始める。
とくにやることもなくカイトの正面に座っていたメイトはそれを眺めた。
一口、二口食べたところでカイトはごちそうさま、とカイトはカップをメイトの方に押しやり、座る場所を椅子からソファへと戻した。
メイトもおう、とこたえて残りのラーメンに手を付ける。
カイトがほんの僅かしか食べないのはいつもの事なので、メイトは最近カイトに食べ物を持ってくるときはなにも食べないでくる。
最初の頃は残してばかりのカイトに無理矢理食べさせていたが、そうすると彼の妹達がひどく怒るので諦める事にしたのだ。
ラーメンを啜るメイトを今度はカイトが見つめ、しばらくはただその音だけが部屋に残っていた。
メイトが何の気無しに上げる度にカイトは眠そうな顔をしており、このままだとまた寝るな、と思ったメイトは食べるのを一時中断してカイトに声をかける。さすがに目の前で寝られるのはカンに障るものがある。
「なんかお前、今日はいつもより眠そうだなぁ」
「んーー、そう?」
「昨日なんかやったのか?」
「なんもやってないよ。いつもとおんなじ」
「そうか」
ぽつぽつとだが返事をさせて、多少はカイトの意識が浮上したのを確認してから残りのラーメンを掻っ込む。
ごっそーさん、とメイトは律儀に手を合わせて、カイト、と声をかける。気になっていることがあったのだ。
「お前、あれから血ぃ飲んだ?」
「えっ、と」
メイトが今と同じように先週ここに来た時、カイトは五ヶ月ほど血を飲んでない事を白状した。
カイトは吸血鬼の中でも古い種で、日光に弱いのはもちろん、人間の血は生きる上で最も必要だ。普通の食べ物でもないよりマシだがただそういうだけで、飲まないわけにはいかない。
元からあまり血が好きではないという変わり者だったが、五ヶ月はいくらなんでも長すぎる。メイトが思わず自分の血を提供しようとしたほどだ。
しかしその時はカイトが、後で飲む、男の血はちょっと、などと言ったのでメイトがひいたのだが、この様子だとまだ飲んでいないようだ。
メイトは一つ溜息をつく。
「なんで飲まないんだ?飲みたくなるんだろ」
「そんなこと、ないよ」
「嘘つけ。前自分で言ってただろ、喉渇くって」
「………」
「喉渇いてるのって辛いだろ。どうしたんだ?」
「…………」
「あいつのせい?」
カイトが俯いて視線をそらす。それは肯定と同義だった。
たった今言った あいつ についてメイトはよく知らない。
知っていたのは、メイトと同じように、人間でありながら吸血鬼に関わっていたという事と、カイトやメイコが あいつ を慕っていたという事。
そしてその あいつ の血をカイトが飲んで、あいつ が今は死んでいるという事だ。
カイトが血を飲んだ事が死の直接の原因なのかはわからない。だがカイトが今血を飲みたがらないその理由に関わっているらしい。
「カイト、もうちゃんと飲め。それでお前が倒れたりしたらみんな心配するぞ?」
「それは、わかってるよ」
「あいつがどう関わってるのか俺は知らないけど、お前があいつの死につられんのはやめときな」
「べつに、死にたいわけじゃない。そうじゃないんだ」
ぎゅっとソファの上でカイトは膝を抱え込んだ。俯いて顔にかかった青い髪の隙間からメイトを見る。
闇の中で、光るわけでもなくその存在感のみで他者をひきつけるその瞳は、人間のそれと同じもののはずなのに、どこまでも異質だった。
長い付き合いだとはいえ、鬼の気配を強くした瞳で見つめられるのに、メイトは未だに慣れない。
「血を飲むと、忘れちゃうんだ」
消え入りそうに漏れた声は、もしかしたら彼の姉弟も聞いたことがないのかもしれない。これほど、血への渇望に塗れた声は。
その声と視線は、メイトの体が僅かでも動くことを許さない。
「あの人の血の味が、どんどん、どんどん他のやつの血の味になってく。それが、嫌だ」
だからもうちょっと、待って。そう言ってカイトは、抱えた膝に顔を埋めてしまう。その姿に、先程までの威圧感はなかった。
彼が得た味覚は半年近く前のものだ。普通ならばもうほとんど風化しているだろう。
ぼろぼろのそれを大事そうに抱えるこの吸血鬼が、人間を捕食する異形が、メイトにはひどく弱々しく見えた。
座っていた椅子からメイトが立ち上がり、カイトの方へと回り込んでその青い髪をくしゃくしゃと撫でる。
「わかった。じゃあ、あともうちょっとだけ待っとくな」
とりたてて優しいわけではない、いつもと同じ調子の声音に、カイトがありがとうを呟く。
「いいから、もう寝とけ。飯も食ったんだし」
そう言ってしばらく頭を撫でているとカイトの体から徐々に力が抜け、ソファにことりと横たわる。
おやすみというメイトの言葉は、角砂糖が紅茶に溶けるように、暗い部屋に浸透していった。
------------
吸血鬼なカイトと人間なメイト
カイトを甘やかせられるのはメイトの兄貴しかいないという個人的認識より
PR