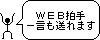ヤンデレからほのぼのまで 現在沈没中
Contents
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
終わりが近付いてきたことにより、レンがさらに厳しい視線で辺りを見回す。缶とそれに一番近い木の間を警戒しながら歩きまわり、どこから走り込まれても対応できる位置を保つ。
だが、そんな彼の歩みがぴたりと止まる。視線は二本ほどはなれた木に固定されていた。
一箇所を見続ければ、それは大きな隙になる。なのになぜレンがそんなことを、と捕まった者達はその視線を追った。
手だった。
幹を這うようにして白い腕が木の裏側から伸びている。どこのB級ホラーだよというアカイトのつぶやきが皆の耳にやけに響いた。
なんとかその腕から視線を外したレンは考える。
あの腕だけでは誰だか判断しきれない。近づけば確実にわかるがその隙に他の二人に缶を蹴られれば本末転倒だ。だからといってあの位置では放置しておくには危険すぎる。
「…地味にイラつく罠ね」
「もうめんどくさいから確認しにいってこいよ。走ればどうにかなるかもしんねーぜ?」
「アカイト、あんたレンにご褒美あげたくないだけでしょ?」
「そういうネルはレンにご褒美あげたいんだろ?」
「なっ?!」
「あれ…アカイト君知ってたんですか?ネルちゃん、レン君にあげるつ」
「なッッに言ってんのハク!!!!嘘ようそうそうそっぱちだから!!変な事言うとでこぴんするわよ!」
「ご、ごめんなさいネルちゃん!私なんか変な事言っちゃったんだねほんとにごめんねあぁもういまさら謝っても遅いよねほんとうにごめんなさい謝るのがおそくてごめんなさいでもでこぴんは痛いからいやなのあっ私なんかが我が儘言っちゃだめだよねごめんなさいむしろ感じょ」
「あーもー!いーから!!あんまりうるさいとレンの邪魔になっちゃうじゃない!」
「もう充分うるさいけどな」
「うるさいわよアカイト!」
騒ぐ三人に溜息をついてレンが口を開く。
怒られるかとネルが身構えたが、レンが投げ掛けた言葉はその予想から外れるものだった。
「みかん」
唐突に何を言っているのだとハテナマークを浮かべる者達など見向きもせず、その視線は再び腕に固定されている。しかし腕になにか変化があるようには思えず、唐突なその行動にネルは戸惑うばかりだ。
しばらく様子を見て、またレンが口を開く。
「コーヒー」
その単語を呟くと、今まで微動だにしなかった腕が動いた。それは、遠目からも確認できるほどの動き。そのまるわかりの反応にネルとアカイトは思わず吹き出した。
レンはニヤリと笑い、堂々と缶を踏み宣言する。
「その腕はルコのだっ!ルコみっけ缶踏んだ!!」
「……あーあ、ばれちゃったかー」
木の裏からルコがレン達の元へ歩いてくる。その表情は苦笑いだ。
己の作戦が見事成功した事を確認し、満足げにレンは再び缶の警戒にあたる。
「行けると思ったのになー」
「アホ?名前わかんなくてもあんな目立ってたら動きにくいじゃん」
「俺は最強の作戦だと思ったんだよ。それでさ、あと誰が残ってんの?」
「テトとリン。で、罰ゲームはカイトにぃ」
「あ、カイトのは知ってる。見てたし」
そこで死んでるしさ、と倒れたままのカイトを指差して笑う。
それをチラりと視線で追ったレンの耳に、カサリ、と落ち葉の鳴る音。と同時に視界に影がわりこむ。
「なっ!」
反射的に缶に向かって走るも、突かれた小さな隙が、決定的なものとなって影との間にある。
それでも、と足にさらに力を込めるがもはや缶までの距離すら僅かで、どんな速度も意味を持たないように見える。
「もらったああああ!!」
力強く叫ぶ声の持ち主は、小柄なピンクの髪をした少女。ルコの背に張り付いていた彼女は気付かれることなく缶に接近し、必勝の間合いで駆ける。
ネルが、ハクが、アカイトが、固唾を飲んで缶が宙に舞う光景を待つ。
走る勢いをそのままに、缶に向かって振り抜かれる右足。硬質な靴が小さなシルエットに迫る。
ブン、と風を破る音。
円を走り抜けるテトに、遅かった、と敗北感にぎゅっと目を閉じる。
しかし、再び開けた視界に映るのは、先程と変わらない光景。
なにがおきたかを把握するより先に、まだそのままに存在する缶にレンの靴が乗せられた。
「テ、テトみっけ、缶、踏んだ!!」
その声に振り向いたテトの顔にはこれ以上ないほどの悔しさが張り付いている。
最後の一蹴り。それを事もあろうが空振りしたのだ。
悔しさに歯を食いしばる彼女を一瞥し、レンは予想外の猛攻を凌いで荒くなった息を整える。
ルコが油断を誘いつつテトを運び、作られた死角からテトが走る。
一度は敗北を覚悟したそれをテトのミスによりとはいえ防いだのだ。レンはふぅ、と息をつく。
だが、ミクには聞こえていた。
テトの高らかに上がった声に混じり、やや離れた木から力強く走る音を。それは確実に缶に向かっていた。
テトとの緊迫した追いかけっこを制した事実は、レンの集中をいとも簡単に散らす。だからレンはそれに気付けなかった。
息をつくままに下がった視界。
その脇から足が、スライディングの形で地面と靴底の間にあった缶をぶち飛ばす。
メキョ、という缶が歪む音。
急に宙に浮いた足をもてあましてレンがバランスを崩し尻餅をついた。
ポカンとするレンの前に、鮮やかに奪い取った勝利に相応しい笑みを浮かべて堂々とリンが立つ。
「甘い!甘いよレン!最後の一人を捕まえなきゃ、鬼は休めないんだよ!」
その言葉が耳に入って、レンの思考はようやく現在に追い付く。それと共に沸き上がる悔しさに声を上げた。
「ああああああ!!!あとちょっとだったのに!!!!」
「ざーんねんっ!ご褒美は私がもらっちゃうよ!」
リンは小さく跳ねてくるりと回り、嬉しさを溢れさせる足取りで転がったままのカイトの元へと向かう。
「どんなのだろうね!」
リンは無邪気に声をかけるが、カイトは地に伏して反応がない。
兎にも角にも、こうして缶ケリは幕を閉じ、二人の名前がメイコとメイトに伝えられた。
その後、勝者であるリンには、メイコが仕事のツテで貰ったという最新型のヘッドフォンと、リンからのリクエストでメイトが探し出した、百年に一度だけ実をつけるという伝説の蜜柑が贈られた。
あまりにも胡散臭い肩書の蜜柑を喜ぶリンにレンは不審がったが、リンに貰った一房を食べた彼はその美味さに戦慄が走ったらしい。
そして、敗者となったカイトに、苛酷な罰ゲームが下されたのであった。
はらり、はらりと落ちる花弁が濃紺の夜に薄紅色を添えた。
僅かに盛りを越えた桜は、風のない夜でも自ら空に舞いおり、その美しさは見る者の心を静かに魅了する。
どの人もゆったりと歩き、それと同じく時もゆるやかに流れているようだ。
この道は、花見の穴場の一つだった。
両脇に植えられた太い桜の木が車一台分ほどの幅の道を美しいトンネルへと仕上げており、住宅街にあるこの道は夜になると車の通りも少なくなって、静かに桜を楽しむ事ができるのである。
この季節によくある、人々がゆっくりと歩き桜を眺める穏やかな風景。
しかし今夜は、その空気がいつもとは違うものとなっていた。
桜のトンネルに見とれながら、ゆっくりと帰路を進む女性。
道の半ばあたりで、一人歩むその背中から声がかけられた。
「今宵も、なんて妖艶な桜なのだろう」
振り返れば、夜に似た青色の髪に、揃いの瞳をした青年が立っていた。
春になるのだというのに黒いロングコートに黒いマフラーをした姿に、女性はたじろぐ。
警戒されているのを悟ったのか、ぎこちなく青年は微笑んだ。
「しかしそれ以上に、あなたは美しい。どうか、 、その血を飲ませていただけないでしょうか?」
唐突なその発言に女性が固まる。
自然な動作で伸ばされた青年の手が触れようかというところで女性は我にかえり、バシンと青年の手をはたいて脱兎のごとく桜並木を駆け抜けていった。
それを見送った青年――カイトは両手で顔を押さえてうああと呻いてしゃがみこんだ。
「も、もう勘弁してください…俺、捕まっちゃう…!!!」
悲痛な叫びは桜の枝に括り付けられた携帯から、家の中で罰ゲームを眺める家族ともいえる存在達へと届けられる。
「おいおいカイト、まだたったの26回目だぞ?まだまだ行ける!夜は長いしな!」
「大丈夫だよカイトにぃ、吸血鬼は夜の間はずっと活動でき、る、から。っははははは!」
「あっははははははは!!よ、妖艶!ようえんとか!!!マジで言ったよこいつあははははは!」
「ねぇカイト、今のセリフ、さっき私が言ったのと違うわよね?艶やかなその喉に僕の牙を突き立ててその甘美な毒のような熱い血を啜らせてください、だったわよね?」
「でもこれ長いから大変だよね。やっぱり練習しておいた方がいいよお兄ちゃん!だから今言ってみよ?」
「だが、ようやく吸血鬼らしさが出て来たのではないか?最後まで言えたのは今のが初めてだろう」
「ははははははは!!テ、テト、むしろこれ、最後までのがつ、辛いんだよ?ははははははははははは!!!!!」
「カイトにぃ、もっとはだければいいと思うよ!きっちり服着てる吸血鬼ってあんまいないしさ」
「なんでリンはこんな偏見もってんだ?ははっ、でも面白いからそれやってみようぜカイト!」
「なぁなぁ、やっぱりさ、それよりも この桜の美しさに惑わされた憐れなオオツルハマダラカを愛という名の熱い血潮で溺れさせてください がいいんじゃね?カイト、そうなんだろ?」
「はははは!!もう最終目標言ってないしそれ!!!」
「……オオツリハダマカラ?なにそれ…」
「違いますよニガイト。オオツルハマダラカといって、蚊の一種です。ルコ、よく知ってましたね」
「ウィッキーに聞いたんだ」
「ウィッキーさん?色んな人とお友達なんですね」
「カイコ、本気?」
「めいとさぁあーん、おしゃけもうなくなりましたよーお?あれ?あれぇ?かいとくんがちいさくなっちゃってますねーえへへへ」
「ああもうハク!飲み過ぎ!!」
「まぁ、はははっ!血を吸う前に戻って来たらもっと酷いのになっから!はははははは!!別に戻ってきてもいいぜ!!」
ぎゃーぎゃーとテレビ電話の前で騒ぐ彼らがまだまだやらせる気満々な事に、カイトは本気で泣きたくなった。
「まぁでも、今までみんな女の子なんだからいいじゃない」
「え?!男が来てもやんなきゃいけないの?!!!!」
「当たり前だろ?罰ゲームは、通行人の血を吸うふりして首にキスする なんだからな」
「ちょ、ちょっと待って!!キスってなに!!!」
「まぁ、祈れ」
「ちょっとっ!!!!!」
「あ、カイトにぃ、そろそろそっちに誰か行くよ!ほら、はだけてはだけて!」
「セリフは俺のでもメイコのでもいいぜ!」
「あ…この人影……」
桜並木の入口あたりに同じく設置されている携帯を見たニガイトが呟く。
「男、だね」
「う…そ、だ……」
携帯の向こう側から大きな大きな笑い声。
励ましか、はたまた嘲りか、ひらりと舞い降りた花びらが、カイトの髪にくっついた。
時刻は10時40分。明るい朝陽はまだまだ遠かった。
翌日、変質者に注意、の紙が張られたとかなんとか
PR