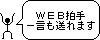ヤンデレからほのぼのまで 現在沈没中
Contents
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
マフィアな感じの話
だいたいカイトとアカイト
ほんのちょっと刺したり刺されたりしてますので、苦手な方はご注意
煙を肺一杯吸い込んで、吐き出す。
組織の他の仲間達と違いめったに煙草を吸わないカイトだったが、この部屋に充満する臭いに胸やけがしたので、床に転がるモノの一つから煙草を拝借したのだ。
しかし5人分の血潮の臭いがたかが煙草の1本で消えるわけもなく、より不快になった空気にカイトは眉をひそめた。
狭く汚らしい部屋に置かれた小さな机。そこの灰皿に既にあった吸い殻の山に1本追加する。
机を囲むようにして転がっている元人間をちらりと一瞥した。
自分が作った死体がそのあとどうなるか、カイトは知らない。それでも、刺しっぱなしのナイフが血の跡も残さずしっかり戻ってくるところをみると、組織の誰かが丁寧に 仕分け しているのだろう。
カイトは血溜まりを踏まないようにして部屋を出た。
非常階段の錆び付いた手摺りの向こうに暗い暗い闇が広がる、日没からも日の出からも遠い時間帯。部屋の中の臭いから逃げるように大きく深呼吸をするが、排気ガスで濁った空気も、彼にはどこか物足りない。
生きるための最悪の手段の一つだった仕事に、いつの間にかどっぷりと浸かっている自分に、彼は自嘲の笑みを浮かべた。
時間帯も加わり、ただでさえ人通りの少ない路地裏に人がいるようには思えないが、音をたてないようにカイトは階段を降りていく。
残り数段、というところでカツンと小さな音がして足を止める。見回しても人はいないようだった。
そもそも、音は足元からのもので、己の足音だろうとカイトは見当をつけた。
足音を殺しそこねるなんてここ最近なかったのだから、随分疲れが溜まっているようだ、とカイトは結論づけると、残りの階段を音をたてずに降りきった。
そのまま1歩、2歩と進んだところで、カイトの左の脇腹に鈍い衝撃が生まれる。
「 っ う 」
振り返れば、恐らく非常階段の下に隠れていたのだろう、薄汚れた身なりの子供が立ち尽くしていた。
偶然立ち会った衝撃からではなく、興奮か恐怖かで震えている姿から、子供が人を刺す事になれていないだろう事が伺える。むしろ、初めてかもしれない。
力を込めずとも徐々に湧き上がる激痛に力が抜けていく。
やがてカイトは立っていられなくなり、雑居ビルの外壁に背を擦るようにして地面にへたりこんだ。その際に刺さった刃物も壁に押し付けてしまい、肉の繊維を混ぜられる苦痛に漏れ出そうな声を、カイトは必死に噛み殺す。
いつ殺されてもしょうがない生活をしているというのに、警戒を怠った過去の己を殴りたい気分にかられつつも、彼は子供の次の動きを待つ。
対象の動きを制限したのだから、次は留めを刺しにくるか、それとも何か物を盗るつもりか。
カイトは立つことができなかったが、どちらにしろ子供が近付いてきたら、腹に刺さった刃物を引き抜いてそのまま刺し返すつもりだった。
一応は詮のようになっている刃物が抜ければ大量の血を失い、失血死する可能性すら少なくないだろうが、カイトにとってそれは些細な事だった。
痛みのあまり明滅する視界で、カイトは己を刺した子供を見るが、闇が顔を隠して次の動作をすぐには読むのは難しかった。
ふいに、張り詰めた空気を断ち切るようにして子供が背を向けて走り出す。逃げられては、カイトに打つ手はないし、どうにかする必要もなかった。要は、そこにあったのはカイト自身の命の問題だけだったからだ。
カイトがあの部屋で何をしていたのか知っているようだったら、次はあの子供を殺すよう命令されるだけだろうし、そうすれば子供が誰か、なんて考える必要も消えるのだ。
知らないのならば子供の事だ。一回刺せば、そこそこ気が済んでそこそこ慢心してそこそこ恐怖にかられ、近付いてこないだろう。
ただ、走り去る後ろ姿の、薄汚れているにも関わらず光るような金の髪がカイトの印象に強く残っていた。
しばらく子供の去って行った闇を見つめた後、カイトはついさっきまで仕事をしていたのだったということを思い出す。
いくらなんでも対象の部屋の下で朝まで眠りこけるのはまずい。
「あー… ちょっと痛いどころじゃない…かも」
立ち上がろうと腹に力を込める度、異物が潜り込んでいるせいで、普段は意識もしない肉が動いている事がわかってしまい悍ましさに眉を潜める。
それ以前に痛みもひどく、歩きだす気にはとうていなれない。
いっそのこと抜いてしまおうか、治療を受けるのと失血死するのはどちらが先だろうか、などと痛みに疼く頭で考える。
傷口だけに集中した感覚に、ふと、赤色が紛れ込んだ。
見慣れた赤にしては、闇の中でもいやに目立つそれに視線を移す。仕事の対象の関係者だったらめんどうだな、とカイトは密かに迎え撃つ用意をしながら、赤色が近付いてくるのを待った。
「 ん?お前、もしかして」
間合いのぎりぎりで足を止めた赤色が呟く。
顔が判別できる距離まで来ており、発色のいい赤色の髪と瞳にカイトはどこか違和感を覚える。見たことのある顔をしているのだ。
これほど派手な色をした男ならそうそう忘れるはずもないのだが、カイトの記憶に一致する者はいない。しかし、見たことがある。
脇腹の痛みも徐々に増して、カイトが思考を放棄しかけたところで、赤色の男が口を開く。
「お前、カイトだろ。メイコから聞いたことある。俺と同じ顔してるやつがいるってよ」
もの珍しげにカイトを眺めた後、刺さったままの刃物を見つけて、なにやってんだよと呆れた声をだす。
そのまま死ぬなよ、とだけ残して、赤色の男はカイトが降りてきた非常階段を登っていく。
ドアが軋む音がしたタイミングからして、彼はカイトが出てきた部屋に入ったようだ。
カイトはじくじくと続く痛みに意識を飛ばさないよう、男が言った先程の言葉を反復する。男の口から出てきたのは、カイトのよく知る名前だった。
メイコとカイトは互いの両親が生きているころからの仲であり、共に生きてきた家族のような存在だ。カイトとは違ってこの区画の賭博場を仕切る立場にまでなっているが、彼女とカイトは未だに親しい。
そういえば、とカイトは先程の男の顔と言葉を思い出す。その話なら、以前カイトもメイコから聞いた事があった。カイトによく似た、アカイトという男がいると。
彼女の知り合いならば、とカイトはこの場から離れることをせず、アカイトという男を待った。
痛みのせいで意識が飛んでいたようで、錆びたドアの音でカイトの意識は浮上した。
ふぅ、と息を吐く音の後、アカイトの気配がおりてくる。
腕が凝ったのか、ぐるぐると回していたアカイトはカイトを見つけると、カイトの存在を忘れていたようで、あぁ、と笑う。
「生きてた?なら報告ついでにメイコんとこの誰か呼んでやるよ」
軽い音をたててアカイトは携帯を開くと、電話をかけはじめた。
ぼそぼそとした会話はカイトまで届きはしなかったが、通話を終えたアカイトの表情で、なんとなく内容に当たりがつく。
面倒だという意思がべったりと顔に張り付いていた。
「メイコの方も今立て込んでるらしい。だからお前は一旦俺んとこだと」
「 君の とこ?」
「そ。面倒だけど、メイコの頼みだし」
断るわけにゃあいけねえよ、と言葉を吐いて、カイトを一瞥する。構わなければよかったという後悔が言葉の裏に、というよりもろくに隠す事すらなく転がっている。
「もしかして立てない?」
「あ、うん」
「立つのは手伝う。だけど後は自力で歩けよ。面倒だからな」
「ありがとう」
差し出された手の指先は黒く、いや、赤黒く染まっていた。
それを躊躇うことなく掴んで、カイトはゆっくりと立ち上がる。
それを確認するとアカイトは、ついて来い、とだけ言って歩きだした。
やや歩調を緩めてはいるのだろうが、それでもカイトには早過ぎてすぐに距離があく。
歩く度に激しい痛みが内側で暴れ、数歩も進まないうちに汗が吹き出し、ビルの外壁についたカイトの手が滑る。
支えを失いうずくまるカイトを見て、アカイトがしばし何かを考えるそぶりをしてから口を開いた。
「なぁ、俺はゲイじゃねぇんだ」
「…ぅ…、…?」
距離が離れているとはいえ、深夜の静寂の中ではアカイトの言葉は容易にカイトへと届いた。
しかしあまりにも唐突なそれは、痛みに麻痺したカイトの思考にさえも疑問符を浮かべさせる。
アカイトはカイトのところまで戻ってきて、赤い瞳で見下ろした。
「だから男に手ぇ捕まれたってうれしかねぇし、そもそも俺は早く帰ってさっぱりしたい」
「なら、俺の事は、置いてってく…」
「そういうわけにもいかねぇんだ。メイコから仕事回ってこなくなる」
そこらへんの死体を勝手に刻むと猟奇殺人扱いにされるしなにより金が入らない、と軽口を叩く。
アカイトの言葉がどこに行きたいのか判断できないカイトは、痛みに呻きながら混乱するばかりだ。
「お前を背負うなりしたら早く帰れるんだけどな、俺は男を背負いたくなんかない。しかし俺は気づいた。意識がなけりゃ人間ってただの肉だ」
カイトに嫌な予感が走る。
引き攣った彼の表情に対し、アカイトはサディスティックな笑みを浮かべて一言呟いた。
「おやすみ」
振り上げた足は、カイトに刺さったままのナイフの柄に下ろされる。
より深く突き刺さったナイフは再び体の内側を傷付け、神経を焼き切りそうなほどの激痛が暴れまわった。
許容量を超えたそれに意識が飛びかけるも、その寸前にアカイトが足を動かし、生まれた痛みに意識を引き戻される。
ぐらぐらと意識を揺り動かされ、カイトは声を上げる事もできない。
どれほどの間アカイトが蹴りつけていたのかカイトにはわからなかったが、唐突に足の動きが止まる。
カイトが無意識に詰めていた息を吐き出すと、それにタイミングを合わせるように、一際強くナイフが踏み付けられた。
「がっ」
今までの比ではないほどの激痛が、ナイフを起点にして全身を荒らし回る。
カイトの思考はブツリと断ち切られた。
PR