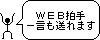ヤンデレからほのぼのまで 現在沈没中
Contents
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
鬼歌・前の続き
三十の日が落ち、旅の人達は山の一番深いところにいた。
旅の人は一月ほど昔、碧の鬼が腰をおろしていた緑に凭れて座り、その正面に鬼達が佇んでいた。
歌が止み、いつかのように葉がさわさわと風にゆらされる音が満ちている。
私はここで死ぬのだけれども、と旅の人が言の葉をゆらす。
鬼達はその命の音を聞き逃すまいとした。
あなたたちには、この肉と魂を今まで共に過ごした時の代償としてあげよう。
そしてその後のあなたたちは、また私のような、酔狂な者に捕まらない限り、人を喰おうが歌を歌おうが、死を選ぼうが自由だ。
自由になったら、私を八つ裂きにして捨て置いていい、だから、最期に少しだけ、言わせてもらってもいいかな。
顔の色は変わらず、ただ声の音だけが徐々に小さくなる。
人に斬られても、鬼に喰われてもいないが、確かに旅の人は死に近付いていた。
私は、幸せだよ、死の時までも。
あなたたちを残して死ぬのは、死を悼んでもらえるのは、とても幸せ。
だけどあなたたちは、生きてほしい。
私が付き合わせた時間よりも長く長く、自由に幸せに生きて。
これはただのお願いだから、選ぶのはあなたたちの自由だけれども。
最期の言葉は、葉の音よりも小さかったが、鬼達にはよく聞こえた。
碧の鬼は少しだけ驚いていた。
あれだけ歌を望んだ旅の人は、歌を歌い死んでゆくのだろうと、漠然と考えていたからだ。
佇む鬼達の前に、死んだ肉。
魂がそこにまだあることは感じる。
だがそれだけで、話すこともなにもできはしない。
碧の少女はただ不思議な気持ちが増すのを感じるだけで、何もできずにいた。
旅の人はもう動かなかった。
鬼達も動かなかった。
風もいつの間にか止み、満月だけが天を昇った。
その月も落ち始めるころ、ようやく時が動き始めた。
始めに、青い髪の青年が、
俺は、あのひとの後にいきます、あのひとのいないところにもう価値はないでしょう。
さようなら、家族達、と告げて、左胸に穴を空け消えていった。
それに続いた黄色髪の双子の子供は、
私と俺は、あのひとの言うように、長く長く、幸せに生きましょう。
さようなら、家族達、と告げて、手を繋いで山を降りた。
赤茶の髪の女性は、
私は、あのひとの事を理解したい、その後に、なにをなすべきか決めましょう。
さようなら、家族達、と告げて、落ちる月を見上げて座り込んだ。
碧の少女は、迷い、躊躇った。
自分がなぜこれを望んでいるのかがまったくわからなかったからだ。
だがやがて心を決め、赤茶の髪の彼女に声をかける。
あのひとを生き返らせるには、どうすればいいのでしょうか。
彼女は嬉しそうな、寂しそうな顔をして呟く。
そう、あなたはそれを選ぶのね。
赤茶の髪の女性が言うに、生き返るには長い時間が必要だという。
百年。
百の年を待ち続けなければならない。
一月があれだけ長く感じたのだから、千と二百の月とはどれほど長いのだろう。
その途方も無い年月に碧の少女は後込みしたが、ただ百年待つだけではまだ足りない、と彼女は言った。
魂が生き返ったとしてもそこに記憶が無ければ意味がない。
その体に染み付いた記憶が薄れないよう、その記憶を完璧に保存する必要がある。
より完全に記憶を保存するには、その体ごとを飲み込み、自らの一部にするしかないのだ。
彼女がなぜ苦しそうな顔をするのか、碧の少女は理解できなかった。
人喰いとは、鬼が鬼である故の行為である。
なにを躊躇う理由があるのかと。
だがこうして、旅の人の首を洞を腕を足を切り離し、その指を口に運ぼうとして少女は理解する。
嗚呼、私にこの人は喰べれない。
その指先に歯を食い込ませ、噛みちぎろうにも顎に力が入らない。
何故だろう、何故なのだろうと、何度も歯をたてるも、どうにも喰べることができずにいる。
もしやこれは、旅の人の罠なのかと、生きていた頃の言葉は嘘だったのかと思った。
呼吸は荒くなり、ただただ力が流れて消えていく、そのような呪いをかけたのかと。
それでは尚更、真実を問うために旅の人を生き返らせねばと、なけなしの力を集め漸く指先を噛みちぎった。
口の中に広がる、人の肉、人の血、人の骨の、慣れ親しんだ味。
その中にただ一つの違和感を少女は感じる。
はた、と思い当たり、その血染めをされた掌を眼にあてた。
初めて流れた涙は、血液よりも塩辛く、カリカリと少女の咽を引っ掻いた。
碧の鬼は、かつて自分が生まれた緑に再び腰掛け、歌いながら百年を待つ
旅の人が迷わずに、この場所にまた還るように
碧の鬼は、かつて彼等と生きた歳を思い出し、歌いながら百年を待つ
旅の人が遺した記憶が薄れ消えてしまわぬように
碧の少女が数え切れなくなるほど、日が落ちてまた昇った。
少女の体には緑が這い、その姿を見止める者も少なくなった。
ただ少女の奏でる歌声だけは、さわさわとたゆたう葉の音に呑まれずに、空へと響いた。
ただ一人のためだけに歌われる歌は、他の人を惑わす事なく旅の人を呼び続ける。
長い永い時が過ぎ、碧の少女の記憶も掠れようかという頃、その翡翠色の瞳が空で何かを捕らえた。
ふわりふわりと、夜の闇とは分け隔たれたあわい光。
いつか見た、あの人の最後の姿。
碧の鬼は体に絡まる緑を振り払い、その光の落ちる場所へと走りだした。
一歩ずつ緑を踏み締める度、薄れかけた記憶が、心が、鮮やかに蘇ってくる。
愛しい、淋しい、楽しい、悲しい、苦しい、恋しい、
百年の間に、いつの間にか抱え込んでいた気持ち。
その全てを持って、その全ての感情の源へと駆けた。
山の中で唯一開けた一角。
白い華の咲き誇るその場所で、緩やかに落ちてくる光を抱き留めた。
するり、と何かが抜けてゆき、代わりに確かな存在が腕の中に生まれる。
いつかのような緩い笑みを浮かべ、何か言おうかしばし逡巡した後、
あなたの歌がずっと聞こえていた。
待っていてくれてありがとう。
と言った。
その言葉に、消え入る事のない音に、碧の鬼は旅の人を強く抱きしめる。
塩辛い涙に顔を染めながら、それでも嬉しそうに、鬼は微笑んだ。
「おかえりなさい!」
PR