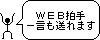ヤンデレからほのぼのまで 現在沈没中
Contents
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
夏企画!
カイコとレンとちょっとカイト
カイコが雪女です
時代設定は江戸とかずいぶん昔のイメージ。あくまでもイメージ。
窓の隙間から、満月の光が差し込んでいた。
朝から降り続いていた雪も今は止み、大雪の後に特有の、息苦しくなるような凜とした静けさが夜を飾っている。
もう慣れきっているはずのその空気になぜかこの日は落ち着くことができず、いやに冴えてしまった目を持て余して、レンはしかたなく天井にある目玉のような木目を数えていた。
しかしそれにもやがて飽きて、隣の布団で眠るリンを怨みがましく見る。すやすやと気持ち良さそうな寝顔は無理矢理起こすのを躊躇わせ、レンはしかたなく小さく息をついた。
それにまぎれて、かたん、と戸口が小さな音をたてた。
風か、と思うも、この静けさの中には風も無い。
ならば間抜けなこそ泥か、と思い至るやいなや、レンはそろりと布団から抜け出す。眠れないこの鬱憤をこそ泥退治をして晴らしてしまおうと考えたのだ。
彼はまだ青年といえる年齢には達していないものの、なかなか腕のたつ少年として村中に知られていた。
家に入るのに物音をたてるようなこそ泥ならば、己の力でどうにかできるだろう、とレンはふんだのだ。
立てかけてある木刀を手にとり、戸口へと近づく。
リンを起こそうか迷いもしたが、彼女を起こすと、この丑三つ時に大声でこそ泥を挑発しかねない。
気付かれないよう足音を殺し、戸口に手をかける。様子を窺うがしかし、戸の向こうに息遣いはなかった。
ドジを踏んだとわかって早々に逃げ出したのだろうか、いやそれにしては雪を踏む足音が聞こえなかった、とレンは頭を巡らせる。
もしや戸口から音が出たのはただの気のせいで、この向こうには誰も何もいないのでは、と思いついたところで、レンは自分のそそっかしさに恥ずかしくなった。なにもいないということは、こそ泥がいることよりもよっぽど現実味があったのだ。
双子の片割れを起こさなくてよかった、と自分を慰めながらも、いやでもなにかあるかもしれない、と最後の悪あがきといった心持ちでレンは戸を引き開けた。
満月と雪のせいでどこか明るい夜の景色。
そこに見慣れぬ藍色がまじり、レンは思わず木刀を握る手に力をこめる。
しかしその手を振り上げる事はできなかった。そこにいたのはこそ泥ではなく、藍色の髪に真っ白の着物を着た、これまた白い肌の娘だったのだ。
娘は、突然開いた戸に驚いたといった風情で、髪とそろいの藍色の瞳を大きく見開いている。
その表情がやわらかい微笑みになったところで、レンはようやく我にかえった。
「あ、あんた、だ」
「しぃ。静かにしなくちゃ、お姉さんが起きてしまいますよ」
人差し指だけ立たせた手を口元に持ってきて、にっこりと笑う。
その笑顔に面食らって、レンは一瞬言葉を失った。
戸を開ける前に、こそ泥を取っ捕まえようと意気込んでいた彼はもうどこかにいってしまっていて、こそ泥に高らかに言おうとしていた、何者だ、何をしにきた、という問いも言えずじまいだ。
口をぱくぱくとさせて声を出す様子の無いレンを静かにしようとしているのだろうと思った娘は、柔らかい笑みのままひそひそとレンに話しかける。
「あの、今夜はお願いがあって来たんです」
「お願い?」
「はい」
先程まで眠れないと言っていた頭もどこかぼんやりとし、鈴のような声に聴き入りながらレンは尋ねる。しかし視線はしっかりと娘に向けられていた。
真っ白な雪原と濃紺の夜空、黄金色の満月を背景に佇む娘。月明かりが藍色の髪と白い着物を夜空と雪原から浮かび上がらせ、まるで今日の夜のようだ、とつまらない事を考えてしまう。
背は低く、歳はレンと同じかそれより下かと思ったが、振る舞いや表情に、彼の双子の姉にはないドキリとするものがまじっているので、もしかしたら彼より上なのかもしれない。
白い着物に、白に近い青色の糸で細やかな刺繍がしてあるのに気付いたところで、娘が お願い を口にする。
「一緒に遊びましょう?」
「遊ぶ…って?」
「もちろん、この真っ白いゆきのはらで」
楽しいですから、と木刀を持っている手を優しく握り、そのまま雪原に一つ歩を進める。
小さくて美しい手に驚いて木刀を落としてしまい、ぼすん、と間の抜けた音と共に雪原に突き刺さる。
ふらり、とレンも娘に続いて一歩踏み出し、その白い雪の上に足跡をつけ始めた。
肌を刺すような冷たい空気の夜なのに、どこか心地よさが感じられる。繋いだ手にひかれて、森に近い開けた場所に出ると二人は足をとめた。
そこで娘は何かに気がついたようで、申し訳なさそうな表情でレンを見つめた。
「あの、ごめんなさい。私、まだ名乗りもしてませんでしたね」
「え、い、いや・・・いいよ、気にしてない。謝んなくて全然いい」
「ありがとうございます」
ほ、と安心したように笑って、娘は改まってレンと向かい合う。
「私は、カイコといいます」
「俺は、レン」
「レン君、ですね。・・お互いに名前も知らなかったのに遊びましょうだなんて言ったのに、ついてきてくれてありがとうございます、レン君」
「う、あ、うん。どういたしまして・・・」
たった今聞いた名前を忘れないように心の中で何度も繰り返しながら、照れくさくてやり場をなくした視線を、とりあえず満月の辺りを漂わせておく。
にこにこと、とてもうれしそうに笑うカイコの、今はレンの手とは離れてしまった真っ白な手を、また繋ぎなおすには何と言えばいいだろうと無意識に考えている自分に気づいてレンは動揺する。
落ち着くために必死に考えをそらしているうちに、この雪原まで来た理由に思い至った。
「あ、ほら、じゃあ何して遊ぶの?」
「うーん、ひとまず、雪だるまでもつくりましょうか」
「わかった」
レンはとりあえず雪を一掴み取った。やわらかな触り心地とは違う針のような冷たさに僅かに躊躇うが、それを両手でぎゅっとにぎって転がすための雪玉を作る。
カイコはレンを見て不思議そうな顔をしており、それに気づいたレンは動きを止める。
「何を作るんですか?」
「雪だるま作るんでしょ?」
「あ、はい。そうです…よね」
「?」
「…多分、私とレン君の雪だるまのつくりかたは違うみたいです」
「転がすんじゃなくて、山みたいにしてから削り出すとか?」
「いえ、あの、そういうのとも違くて…」
カイコは俯いて、そっか、ちがうんだ、と小声で呟いているのを聞いて、レンは何か悲しませるような事なのだろうかと不安になる。
しかしよくよく見ると、カイコは悲しんでいるのではなくどこか恥ずかしそうにしていて、レンは首を捻った。
それでも頭の中での折り合いがついたらしく、カイコは顔を上げると、今からつくるのでちょっと見ててください、とレンに告げた。
四歩ほど下がってレンと距離をとり、深呼吸をしたあと、カイコがゆるりと腕を上げる。
どう作るのかと見つめるレンの前で始まったのは、舞だった。
カイコ自身が奏でる、夜の雪原に寄り添うような歌声に合わせて、流れるように舞う。
白い着物が月明かりの中を泳ぎ、藍色の髪がさらりと揺れた。
あまり激しくないとはいえ、動き回っているにもかかわらずカイコの声は乱れる事なく響く。
するとやがて、カイコの歌と舞に同調するように、辺りの雪がざわついた。既に地に落ちたはずの雪がまたふわりと浮き上がり、流れ始めたのだ。
常ならばありえない光景。しかしそれを見るレンの中には恐怖や悍ましさ、嫌悪などの感情は不思議と生まれなかった。ただずっと、綺麗だ、という感情があるだけだ。
いつの間にか歌声も止み、カイコが恥ずかしそうな、でも誇らしげな笑みで佇んでいる。そう長い時間ではなかったのだろう、カイコに疲労の色はなかった。
「できました」
我に返ったレンは、彼女を取り囲むようにして、三つの雪の塊ができていることに気付いた。
驚いたレンの手を取り、カイコがにこりと笑う。
「レン君も一緒にやりましょう。二人なら、声を合わせるだけでもつくれますから」
答える間もなくカイコが歌い始め、レンもいつのまにか、それに合わせて聞いたことも無い歌を歌い始めていた。
カイコが言った通り、先程と同じように雪が浮き上がり始めてふよふよと漂う。
その景色も十分美しかったが、レンにとってはカイコと歌を奏でている事が、それ以上に心を充実させていた。
この瞬間のためならなんでも差し出せる。
そんな思いを心に残しながらも、夜はふけていった。
窓の隙間から、朝の光が差し込んでいた。
かたん、と戸口がたてた小さな音で、レンは目を覚ました。隣の布団では彼の片割れであるリンがすやすやと眠っている。
彼女を起こさないように布団から出て戸口に向かう。
その途中で、戸の向こうにいるのがこそ泥の類だったらどうしようか、という考えが過ぎったが、そんなことはないだろう、とすぐさま否定した。
いくらなんでも、やや早い時間とはいえ朝に盗みを働こうとするこそ泥などいないだろう。
木刀を立てかけてある壁にちらりと視線をやったが、そこに木刀はなかった。別の所に放ったままか、と結論づけて、レンはがらがらと戸を開けた。
戸の向こうには日光と雪のせいでいささか目に痛い朝の景色。
そこに、どこか既視感がある藍色がまじり、レンは疑問に思う。
見たことがあるような藍色なのだが、生憎彼は目の前にいる青年など会ったことがなかった。
レンよりも歳が上らしい彼は落ち着いた優しそうな瞳をしているが、それでも朝から訪問されるような覚えは無い。
「あんた、だれ?」
「木刀が落ちていたから、この家の人の物かと思って」
「そりゃ…ありがと」
木刀を受け取り、戸を閉めようとしたところで藍色の青年が、それと、と言葉を続けた。
「俺の妹と遊んでくれてありがとう。すごく喜んでた」
「妹…?」
「カイコの事だよ。俺はあの子の兄なんだ。まぁ、双子だからあんまり関係はないんだけどね」
名前を言われてレンはハッと思い出す。青年の藍色は彼女のものと同じだったのだ。
昨晩の、心が満たされ、全てがどうでもよくなる ような経験が脳裏に蘇る。
あの時の自分は酒に酔ったようにどこかおかしかったのでは、と思うような記憶だった。彼女と歌うだけの事があまりにも幸福すぎた、とレンは思いかえす。
しかし、その思いを生んだときの彼がどのような状態であったかにかかわらずに、それは今も彼の中にあった。
感情を持て余しながら、レンは彼女の兄を名乗る青年に尋ねる。
「あの…こう言うのは失礼なんだけど、カイコは、何?」
「君は何だと思う?」
「そ れは 、」
記憶を辿ると、レンには彼女が雪の化身や、精霊であるように思えた。しかしそれは堂々と言うにはやや恥ずかしい言葉で、レンはもごもごとするだけで口に出せずにいる。
そんなレンを見て、カイコとよく似たようにクスリと笑うと青年はにこやかに言う。
「カイコは、雪女だよ」
「ゆき…おんな?」
「そう。だから、何回もカイコと 遊んで いると、山に迷い込んで魂を食べられる」
「…それって、」
「うん、君 は死んでしまう」
「そん な」
「俺としては、君にはカイコと遊んでもらって、食べられてほしい。そうすればカイコは、君が生きてるうちは楽しいし、君を食べて新しい糧にできる。君には悪いけど、俺はあの子と家族だから、こんな風に思うんだ」
そんな事を笑顔で言う青年が信じられなかった。
しかし、記憶に残る彼女が雪女だというのは、やけにしっくりとした。彼は本当の事しか言っていないのだろう。
ふと、レンは気付く。
信じられなかったのは青年が言った言葉ではなく、
「また、カイコと遊んであげてね」
自分自身の、彼女に食べられても構わない、という思いだった。
-----------
続く・・・確率は限りなく0に近いです
素敵なリクエストをくださった琴葉様、ありがとうございました!!
PR