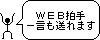ヤンデレからほのぼのまで 現在沈没中
Contents
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
夏企画!
カイトとアカイト
カイトが魔物の長的ななにか
ファンタジーっぽいですね
崩れた家の残骸が燻り、発せられる熱が景色を歪ませる。
一晩で変わり果てた村はそこに生きていた人々の姿も似合いのものとしてしまったらしく、黒い煤にまみれた瓦礫の下からいくつもの人間のかけらが覗いていた。
そんな中で、一人の赤髪の青年が瓦礫を蹴散らしながら歩いている。
肉を焼く酷い臭いを防ぐためか、首に巻き付けた赤いマフラーを口元にまで引き上げている彼は、なにかを探しているようだった。
未だ赤く焼けている物すら蹴り崩し、その下にあるものをざっと眺めてからまた次の瓦礫を蹴り飛ばす。
なにもかもが壊れてしまったような景色で、彼は絶望するでもなく淡々と作業を続けた。
やがて、その動きにめんどうくさそうなものが混じり始めた頃に、彼の視線が一点に定まる。瓦礫の上に倒れた焼け焦げた死体。今までのものと違い埋まっていないそれの元へ、彼は足を進めた。
細かいものも柔らかかったものも気にとめる事なく、瓦礫の上に突っ伏す死体を踏み付けて止まる。
それの指指す、数メートル先の瓦礫の山を一瞥し、彼はため息をついた。
マフラー越しのせいで、僅かにくぐもった声が乾いた空気に響いた。
「お前、なにやってんだよ」
そこにいたのは奇妙な青年だった。
力なく瓦礫に背を付けているが、左腕だけが肩と水平に瓦礫に張り付いている。それを縫いとめているのは剣の類なのだろうが、刃の部分が全て腕に潜り込んでおり柄しか見えていない。
よくよく見れば、その胸元にも上方から斜めに振り下ろしたように大剣が埋まっており、そこを中心として黒い跡が彼の服を染めていた。
命の残滓さえも見当たらないようなそれが、しかしピクリと体を動かす。
ゆるりと顔を上げ、黒く汚れた髪の隙間から青い瞳が覗いた。
周囲の惨状から掛け離れた涼やかな瞳が、見慣れた赤色を見つけた途端にあたたかな色を宿す。
「アカイト、久しぶり…でもない、ね」
「暢気な事言ってんじゃねぇよカイト。ったくテメェ、こんなとこに張り付いてんなよ。肉くせぇ中歩き回らせやがって」
「ごめん、思ったより手強くてさ」
「馬鹿が。相手が強いんじゃなくてテメェが貧弱なだけだろ」
「…あはは」
軽く笑って、カイトは左腕を動かそうと力を込める。
しかし剣はびくともせず、右腕を使おうにも胴体が動かないので届きもしない。胴体のそれはあまりにも深く突き刺さり、片手で抜くには困難だった。
しばし悪戦苦闘するも無理だと悟ったカイトは、その様子を面倒そうに見ていたアカイトに訴える。
「えっと、悪いんだけど、抜いてもらっていい?」
「……後で飯用意しろよ」
「ありがとう。あとできれば、優しく抜いてもらえると嬉しいんだけど…」
「オプションは別料金になるけどいいか?」
「デザート付ける」
「よしわかった、その剣が何回蹴ればお前の腕裂いて抜け落ちるか試してやるよ」
「え、デザートじゃたりないの?」
「当たり前だろ。ンなもん当然飯一回分に入ってる」
「あー、じゃあ………どうしよう…」
「次の襲撃、俺にやらせろよ。それでいい」
「アカイトがやると後始末めんどくさいんだけどな…」
「よっしじゃあ一発目いくぜ!」
「わかった、次のとこは任せるしご飯もデザート付けて用意するから、優しく…!」
「りょーかい」
アカイトがニヤニヤとわらいながら、一先ず左腕を貫く剣に手をかける。
まだそれほど剣は動いていないのだが、カイトは小さく苦悶の声を漏らした。
ぐっと一度強く引いたところで、アカイトが違和感を覚え手を止める。
カイトは訪れる痛みに備えていたのだが一向にアカイトが剣を抜こうとしないので、不思議そうにアカイトに目をやった。
「どうかした?」
「お前これさ、くっついちまってるぞ」
「うわ…やっちゃった」
「これじゃあ優しくもなにも言ってらんねぇわな」
「うっそ…やだな…」
「回復力が異常に強いだけとか、本当、使えねー」
剣が刺さったままの状態でも傷を塞げようするはたらきのせいで、剣と腕の筋肉とが癒着したようになってしまっているのだ。これを抜こうとすれば、かなりの苦痛を味わう事になるだろう。
おそらく同じ事がおきているだろう胸部の大剣を見て、カイトは魂すら飛ばしているような力無いため息をついた。
「もういいや…一思いにぐいっとやっ「はいよ」
「っぐ あぁああ!」
カイトの呟きの直後に、なんの躊躇いも無く左腕の剣をアカイトは引き抜いた。
ズルリ、と纏わり付くものごと引きずり出す感覚が柄を通してアカイトの掌に伝わる。
大量の血が溢れ出すがその勢いもすぐさま弱まり、目に見えるほどのスピードで傷が塞がっていく。
引き抜いたせいでより大きくなり内側を覗かせていた傷口も、赤い線が引いてある程度にしか見えなくなったところで、カイトは詰めていた息をようやく吐き出した。
「ふ、ふいうち?」
「早いほうがいいだろ?」
「そだ 、け ど 」
「で、次はそっちだな」
「まって 、 おれ、じぶんでやるから 」
傷は塞がったものの力が入らない腕をぷらぷらとさせてから、まるでその腕に重りを付けたような、苦しそうな動作で大剣の柄に手を置く。
左手ごと握りこむようにして右腕も置き、カイトは力を込めるが抜けそうにない。剣は僅かに動くものの、その度に激痛が走り力が抜けてしまうのだ。
見かねたアカイトが大剣の柄を強く引くと、内側が掻き混ぜられたせいかカイトの口から血が溢れ出す。
「がっ」
「お?」
さすがに予想していなかったのか、アカイトはやや驚いて手を止めたのだが、また大剣が刺さったまま傷口が塞がったら面倒だと思い至って強く大剣を引き抜いた。
瓦礫に縫い付けていたものが抜き取られ、倒れ込むカイトをアカイトは一歩下がって避ける。
建物の破片の上に俯せになっているカイトの頭を靴先で二、三回小突くと、脂汗をかきながらもカイトがゆっくりと立ち上がった。
ざっくりと開いていた傷も塞がり、口元の血を袖で適当に拭うと、カイトは息をはいた。
「痛かった…久しぶりにこんなに痛かったよ…」
「つーか、えらく簡単に封印されるなお前…昏倒させて張り付けにするだけで行動不能じゃねぇか」
「いや、いざとなったら自力でできるけどさ、無理矢理やるからすごく痛いんだよ」
「そんぐらい堪えろ!」
「うわっ」
アカイトの放った蹴りをうけて、カイトはつんのめりながら瓦礫の上を進む。
ようやく姿勢が安定したところにあったのは、先程アカイトに踏まれた死体だった。
大剣の持ち主である死体を見つめるカイトに、アカイトは横にならんで声をかけた。
「もう気はすんだろ」
「なんの?」
「こいつのせいでミクが怪我したから、お前一人でこいつ潰しに来たんだろうが」
「…メイコ、怒ってた?」
「た、じゃなくて、る」
「あー…」
とぼとぼと死体を踏み越えて歩きだす。
カイトは頭を抱えて空を仰いだ。
「まぁ、お前一人で行くのが1番被害はないのは事実だけどな」
「でもさ、それ言ったらメイコもっと怒るよね…」
「だな」
「うわー、どうやって言い訳しよ…」
「ははっ、もう素直に殴られとけよ」
カイトは助けを求めてケタケタと笑うアカイトを見つめるが、それに気付いても彼は笑い続けている。
ため息をついて、そのまましばらく歩いた二人は村の中心で足を止めた。
アカイトがまだ小さく笑いながらも、ぐるりと辺りを見回す。
「しっかし可哀相に。一応は相打ちにのはずなのにお前が相手だったせいでボロ負けじゃねぇか。ほんとタチわりぃな」
「いいんだよ。途絶えないために俺がこの位置にいるんだから」
「はいはいわかってるっての、魔王サマ」
カイトが呟いた魔法により、彼を中心として村があった位置を青い炎が埋め尽くす。
先程までいたるところで燻っていたものとは違い温度を持たない炎は、触れていたものを巻き込んで消え去った。
朝日の中でくっきりと浮かび上がった二つの人影も刹那のうちに掻き消え、かつて村であったそこは、何一つとして残らなかった。
---------------
趣味丸出し!!
一応、ボカロさん達が魔物な感じの世界観なんですが、どんな動機で人を襲ってるのかは知りません(あら?
多分マスターの命令とかじゃなでしょうか(おいおい
どこが1番書きたかったかは言わずもがなあそこです
PR